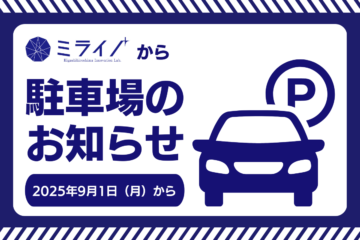小さな気づきが、地域の未来を変えるかもしれない ―ミライノ⁺賞受賞インタビュー|武田高等学校「広島の地域福祉と未来のためにできること」

「福祉って、自分にはまだ遠い話だと思ってた。でも、地域の声を聞いて“私たちにもできることがある”って気づいたんです」
そう話すのは、JICA×ミライノ⁺ 探究×未来:高校生がデザインする社会課題解決コンテストで「ミライノ⁺賞」を受賞した武田高等学校の3人。
今回の発表のテーマは、「広島の地域福祉と未来のためにできること」。
「福祉」というと、医療や介護など専門的で制度的な話に感じがちですが、彼女たちはそれを「すべての人が安心して暮らせる“まちのしくみ”」と捉え直し、身近な課題から考え始めました。
舞台は、竹原市吉名町にある高齢者の集い場「なでしこの会」。
実際に足を運び、お年寄りの方々に話を聞く中で、「病院が少ない」「交通手段が限られている」といった問題に加えて、「話し相手がいない」「気軽に出かける場所がない」といった“孤独”や“つながりの不足”が深刻な課題であると気づきます。
そこで彼女たちは、「移動スーパー」「お裾分け文化の再活用」「デマンド型の交通支援」など、地域の人たちが無理なく関われる“やさしい支え合いの仕組み”を提案しました。
さらに、行動経済学の「ナッジ理論(つい動きたくなる仕組み)」を応用し、自発的な交流が生まれる仕掛けづくりにも挑戦。
「やった方がいい」から「やってみたい!」へ――
一人ひとりの気づきが、地域の未来を変える小さな力になる。
そんな視点で福祉をとらえた、等身大で温かい探究、社会課題解決の発表でした。
3ヶ月前に終わったコンテストをきっかけに、今もなお彼女たちは「問い続けること」をやめていません。
今回、ミライノ⁺で3人に再会し、その探究の軌跡と、変わった視点、そしてこれからの想いを聞きました。
登場人物のご紹介(写真の並び順つき)

- 元谷莉子さん(左):音楽好き。エレクトーンを弾き、Official髭男dism(ヒゲダン)やVaundyなどをよく聴く。
- 畠京花さん(中央):美術部所属。ジャンルを問わず漫画を幅広く読む。
- 八木安滋さん(右):ダンス部所属。スポーツ系アニメ(「ハイキュー!!」「ブルーロック」など)好き。
- 岡野:東広島イノベーションラボミライノ⁺ナビゲーター(今回のインタビュアー)↓

探究チームに聞く!まずは自己紹介から
岡野: 今日は、JICA×ミライノ⁺ 探究×未来:高校生がデザインする社会課題解決コンテストでミライノ⁺賞を受賞した皆さんに来ていただきました。まずは自己紹介をお願いします。
八木: 八木安滋です。ダンス部に所属しています。
畠: 畠京花です。美術部に入っています。
元谷: 元谷莉子です。音楽が好きで、エレクトーンを弾いています。
学校生活で今ハマっていることは?
岡野: 最近ハマっていることとか、学校生活で楽しいことってありますか?
八木: アニメにはまってます。「ハイキュー!!」とか「ブルーロック」みたいな、スポーツ系のアニメが好きです。
畠: 私はいろんな漫画を試し読みしてます。ジャンルは決めず、広く読んでいます。
元谷: 音楽を聴くのが好きです。ヒゲダン(Official髭男dism)やVaundyなど、J-POPやロックをよく聴きます。
なぜ「地域福祉」をテーマにしたの?
岡野: まずは今回の探究テーマ・社会課題解決のテーマとして、「広島の地域福祉と未来のためにできること」を選んだきっかけを教えてください。
元谷: 学校の探究活動「広島の中の私」という単元で、それぞれが興味のある分野を出し合いました。
福祉に関心があった私たち3人が自然と集まりました。
岡野: 実際の調査ではどんなことを?
元谷: 竹原市吉名町の「なでしこの会」という地域サロンに行って、住民の方々に話を聞いたり、活動に参加させてもらいました。
岡野: どんな言葉が印象に残っていますか?
元谷: 病院が少ないとか、交通の便が悪いといった話もあったんですが、「話し相手がいないのがつらい」という声も多くて。
若者からすると見落としがちだけど、実は大きな問題なんだと気づきました。
フィールドワークを通して見えた“地域のリアル”とは?
岡野: 八木さんと畠さんは、元谷さんの話を聞いてどんな印象を持ちましたか?
八木: 曽祖父が家で介護を受けていたこともあり、共感する部分が多かったです。
広島の中だけでも改善できることがあるよねって3人で話しました。
畠: 私の地域も高齢化が進んでいて、交通も不便です。
他の地域でも同じような課題があるんだなと改めて実感しました。
実際の体験を、どうチームで共有したの?
岡野: 情報共有やプレゼンづくりで苦労したことはありましたか?
元谷: 仲が良いので共有はスムーズでしたが、発表用のスライド資料をどうやってわかりやすく視覚化するかに苦労しました。
一番伝えたかったメッセージは?
岡野: 今回のコンテストの6分間の中で一番伝えたかったのは?
八木: 地域の課題って子ども一人では解決できないからこそ、人と協力して動くことの大切さを伝えたかったです。
ミライノ⁺という場所に来てみて
岡野: 今日訪れてもらった「東広島イノベーションラボ ミライノ⁺」の印象はどうでしたか?
八木: (コンテストに出る前)名前は聞いたことがあったんですが、詳しくは知らなかったです。
元谷: 担任の先生からコンテストの案内をもらったときに初めて知りました。
岡野: ここは「人やアイデアが集まり、新しい価値を生み出す」ことを目的とした、東広島市のイノベーション創出拠点なんです。
みなさんに知ってもらえて本当によかったです!
自分たちのアイデアが広がるとしたら?どんな未来?
岡野: 今取り組んでいるアイデアが、もしもっと広がるとしたら?
八木: 高齢者福祉だけでなく、ユニバーサルデザインなど、他分野にも展開できたらと思います。
探究が進路や価値観に与えた影響
岡野: 探究活動を通して進路や価値観に変化はありましたか?
元谷: 医療と福祉をつなげて地域に貢献したいという思いが強くなりました。
畠: 介護以外にも心理学や行動経済学など、いろんな視点で考えるようになりました。
八木: 看護にしか興味がなかったけど、「こんな職業もあるんだ」と新しい世界が見えました。
これから探究に挑む後輩たちへメッセージを
岡野: 後輩たちに一言お願いします。
八木: 大人と同じ目線で社会を見られるのが探究の面白さ。楽しんでください!
畠: テーマから連想して広げることで、新たな発見があります。
元谷: 斬新なアイデアが出なくても、人と話すことで新しい視点が得られます。
編集後記:問い続ける高校生たちと、未来を語る時間
コンテストから3か月。少し緊張しながらも、しっかり言葉を届けてくれた3人の姿が印象的でした。
高校生と大人が対等に話すこと。そこにこそ、未来をつくるきっかけがあるのかもしれません。
東広島イノベーションラボ ミライノ⁺では、2025年8月19日(火)に、高校生向けの「東広島高校生アイデアラボ」を予定しています。
ぜひ、あなたの“問い”を持ち込んでみませんか?
あなたのアイデアが、社会を動かす“はじまり”に。
昨年度はコンテスト形式で発表の場を設けた「高校生アイデアラボ」。
今年は、“アイデアをビジネスの視点から磨く”ことに焦点を当てたブラッシュアップ型ワークショップとして実施します。
講座・相談・発表の3ステップを通じて、より実践的な学びと成長をサポートする構成です。
学校での探究活動や日常の中で生まれた「気づき」や「問い」を、“ビジネスプラン”という形で社会に届けてみる。
特別な準備はいりません。いま「やってみたい」があれば、それがはじまりです。
東広島 高校生アイデアラボ申し込み(本イベント申し込みはこちらをクリック)
イベントの詳細はこちらから▼

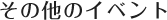
-360x240.png)